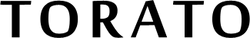ペッレ モルビダ 干場義雅氏インタビュー Part.I

本質を知り、優雅さを求める大人のためのブランド「PELLE MORBIDA(ペッレ モルビダ)」。“旅の理想形”である船旅をモチーフとし、そのコンセプトを基に生み出されるバッグの数々は、まさに成熟した大人にこそふさわしい。このブランドを創ったのは、クリエイティブディレクターを務める干場義雅氏。“ちょい不良(ワル)”という言葉を産み出し、人気雑誌『LEON』や『OCEANS』の立ち上げメンバーの編集者としてヒット企画を連発し、テレビやラジオなど様々なメディアでもお馴染み。現在は、講談社のウェブマガジン『FORZA STYLE』の編集長として活躍。今回は、干場氏の生い立ちから、自身のファッション観を確立するまで、そして現在のペッレ モルビダなど多岐に渡る活躍と、3回に渡ってご紹介する。
干場義雅氏プロフィール
1973年東京生まれ。雑誌『LEON』の創刊に参画。ちょい不良(ワル)ブームの立役者としてヒット企画を手掛ける。その後『OCEANS』を立ち上げ、副編集長 兼 クリエイティブディレクターとして活躍。『STORY』や『Domani』といった女性誌をはじめ、新聞、テレビ、ラジオ、イベントなど、メディアの枠を越えて活躍する傍ら、ANAショッピングastyleのクリエイティブディレクターとして機内誌と連動するECサイト『旅するジェントルマン』を監修。現在は、東京FMのラジオ番組『SEIKO ASTRON presents World Cruise』のメインパーソナリティやテレビのファッションチェックコーナー、ミドルエイジ男性向けデジタルマガジン『FORZA STYLE』編集長など多方面で活躍中。著書は、『干場義雅のお洒落の本質』(PHP出版)、『干場義雅の色気と着こなし』(宝島社)、3冊目となる『干場義雅が教える大人のカジュアル(仮タイトル)』(日本文芸社)は2017年の10月に刊行予定。PELLE MORBIDAのクリエイティブディレクターは2012年から就任。
三代続くテーラーで育った幼少期
―まず始めに、干場さんが編集者になるまで、どんな風に歩まれてきたのかお伺いできますか。
実は、自分の家は三代続いているテーラーでして、僕が継げば四代目でした。父がいつもスーツを作っている工場(こうば)に家が隣接していて、父がイタリアやイギリスの生地やスワッチ(素材見本のこと)などに囲まれて、スーツを縫ったり、ミシンをかけたり、スーツを裁断したりしている姿を見ながら育ちました。
幼稚園のときに、スーツを一着、親父に仕立ててもらったことを覚えています。次に小学校を卒業するときには、金ボタンの紺のブレザーを作ってもらいました。それにグレーのフランネルのパンツを履いたりして。でも、そのときは「なんて窮屈な服なんだ」と思っていました。なんせ、その頃に僕がハマっていたのは、「キン肉マン」や「キャプテン翼」ですからね。サッカー少年だったので、ナイキやアディダスみたいなスポーツウェアばかり好きで着ていたので、そんな親父が作ったような堅苦しいクラシックな服は正直すごく嫌でした(笑)
中学で出会った親友、「NUMBER (N)INE」元デザイナー宮下氏
―小学生だったらそう思うかもしれませんね(笑) では、中学生ぐらいになったらどうでしょうか。ファッションも変わってくる時期かなと思います。
そうですね。中学生のときに、僕の人生で決定的にファッションを好きになるきっかけがあったんです。大親友ができたんですが、その友達がめちゃくちゃかっこよかったんですよ。後に「NUMBER (N)INE(ナンバーナイン)」※1っていうブランドができるんですが、そのデザイナーをやっていた宮下貴裕さんです。実は僕の同級生で、中学2年生ぐらいのときに大親友になって、もうどこに行くのも一緒で。その当時は「アメカジ」や「渋カジ」っていうファッションが流行り始めていましたが、渋谷、原宿、上野、御徒町……。東京中のオシャレと言われているお店は本当に全部行きましたね。もちろん当時はあまり買えなかったので、古着なんかを買いながら、少ないお金で上手にお洒落を楽しんでいたような気がします。このことが、僕が洋服を好きにさせたきっかけだったと思います。
高校生になると、“渋カジ”みたいなファッションが流行っていましたが、僕は本当にオーソドックスでベーシックな、白のラルフ ローレンのシャツやブレザー、グレーのパンツなんかが好きでした。正統派のトラッドファッションですね。破けたジーンズにレッドウイングを履いたり、長髪にしたりもしていたんですが……。その宮下っていう友達が「干場は、トラッドでベーシックなほうがかっこいいよ。そのままでいったほうが絶対いい」って言って。それからですね、現在のベースとなるような、トラッドが根底にあるスタイルが好きになっていきました。
―そこで、ご自分のスタイルが固まってきたということでしょうか?
まだそのときは少しだけですね。それから、高校を卒業するときに、親に「〇〇大学受ける」って言って受験料を30万ぐらいもらったんですが、全部洋服や遊びに使ってしまって無くなってしまいました(笑) 試験を受けるのに1校当たり3万円ぐらいかかるんですよ。それを10校ぐらい言って30万円。でも、全部、使ってしまったので、当然大学は行けず働くことになりました。渋谷の「TOP DOG」っていうお店でアルバイトしたり、セレクトショップの「BEAMS」に友達のツテで入れてもらって販売の仕事をしたりしました。そこで、先輩たちに洋服のことをいろいろと教えていただきました。
『POPEYE』のモデルで初めて雑誌編集者に出会う
―それから編集者になりますよね。そのきっかけは?
雑誌の世界に入ったのは、実はその頃です。週5日間、販売のアルバイトをしていたんですが、休みのときに宮下に誘われまして。「『ポパイ』が表参道でスナップやってて、スタイリストの人が来てほしいって言ってるから、一緒に行こう」って言われて。それで行ったら、次の号にドーンと大きく掲載されて、スタイリストの人にも「君らかっこよくてセンスもいいから、読者の代表としてPOPEYEのモデルになってくれ」って言われたんですよ。モデルって言っても今の読者モデルみたいな感じですが、それで週5日間BEAMSでアルバイトをしながら残りの2日間は読者モデルをやるようになりました。
撮影に行くと必ずスタイリストやカメラマン、ヘアメイクの方がいて、終わると「みんなでご飯食べに行こう」っていう流れになるんですが、そういうときにお金を払っていたのが、ある人だったんですよ。その方は撮影のときは、ほぼ何もしていないように見えていたんですが、お金を払うときは全部払って、ファッションもお金を持っていそうな感じ。「一体、この人は何なんだろう」って思っていたら、その人が実は一番偉い編集者の方だったんです。僕はその人に「少年」って呼ばれていて、「少年! 今度また撮影やるから、〇〇に朝5時までに来なさい」って呼ばれたりしていました。
―そこで編集者という仕事を初めて意識しました?
そうですね。それまではスタイリストもいいなと思っていたんですが、よくよく話を聞いたら編集者が雑誌のページを作っていて、そのスタイリストの人にも仕事を発注していると。それで、「編集者になったら、もっといろんなことができるんじゃないか」と思い始めていたら、友達の紹介で別の編集長の方と知り合いまして、雑誌の編集者をやりたいということを話しました。
ところが、その方に「君は大学を出ているか?」と聞かれまして、「出ていません」と正直に伝えると、「テレビだって、雑誌だって、マスコミっていうところは、大学を出ていない人は絶対無理」って言われたんですよ。「そこを何とか」って食い下がったら「じゃあ何ができる?」と聞かれたので、「僕、洋服のことだったら誰にも負けないです」って断言しちゃったんです。そうしたら「そこまで言うんだったら、じゃあ1回バイトみたいな感じで見てやるよ」って言われて。ちょうど20歳ぐらいのときですね。
そこから出版社のアルバイトをやるようになり、3か月間誰よりも早く出社して、テーブルを拭いて、灰皿片づけて、いろいろやっていたら、「編集者になっていいよ」って言われました。株式会社ワールドフォトプレス、『モノ・マガジン』を発行している会社ですね。
『Esquire』で初めてのミラノコレクション
最初は『MA-1』というストリートカルチャーの情報誌をやっていたんですけど、2年ぐらいで無くなってしまって。それで次はモノ・マガジンに配属されたんですが、自分としてはファッションをやりたい気持ちが強かったので「どうしようかな」って思っていました。そうしたら、人気スタイリストの喜多尾さんから「お前みたいなファッション好きな編集者を探している会社がある。入社試験が難しいらしいが、受けてみたら?」って言われまして。それが『Esquire(エスクァイア)日本版』っていう、もともとアメリカの雑誌の日本版です。
でも、受けてみてわかったんですが、その出版社の人たちはみんな秀才ばっかりだったんですよ。編集長は東大出ているし、僕の上司は、上智やICU。みんなも有名大学で。社長面接、担当面接、編集者面接……みたいな感じで面接が4回あったんですが、大学を出ていない奴が入れるわけないと思いました。でも、奇跡的に試験に通っちゃったんですよ。当時は「うわー!こんな雑誌に!?」って感じでしたね。
―当時はおいくつですか?
23歳ですね。それで、入社したらすぐに「海外に行け」って言うんですよ。入った瞬間にドイツに行かされて、バーゼルやジュネーブといった場所で時計の取材を10日間ぐらい。戻ってきたら、今度は1人で「ミラノコレクションを取材してこい」って言われました。びっくりしたんですが、実は昔からミラノコレクションを見てみたいなって思っていたんです。
少し前から海外のファッション雑誌、洋書もたくさん見ていて、その中にすごくかっこいい二人組がヨーロッパの町中で、サングラスをかけて、いいスーツを着て、スパスパとタバコを吸いながら、待ち合わせをしている風景の写真があったんですよ。その二人組がファッションディレクターっていう肩書で。「この二人、超かっこいい。こんな風になりたい」と思っていました。
そう思っていたら、もういきなりミラノに行けちゃうことになったんです。英語もイタリア語も話せないので身振り手振りで。イタリアで地図を見ながら悩んだりして。いろんな業界の人を見かけては「すみません、東京から来て何にもわかってないんで教えてください」って頭を下げて教えてもらいました。それが繊研新聞の方だったり、伊勢丹研究所のバイヤーの方だったり、BEAMSの偉い方だったり。そういうすごく上の方々に本当に可愛がってもらっていろいろ教えてもらいました。そのときの方々には、今でも仕事でお会いしたりしますね。